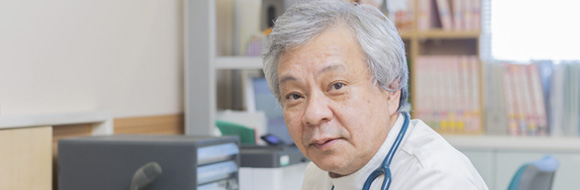病診・診診連携実績
他の病院・診療所と連携を図り、専門的な診療や包括的な治療を行っています。
- 病診連携とは
- 簡単に言うと、病院と診療所の連携です。病院と診療所が緊密に連絡を取り合うことで、包括的で一貫性のある医療を患者様に提供することが可能となります。この二つの医療機関の連携が病診連携です。
- 診診連携とは
- 医療の進歩で、より専門的な診療が要求されています。専門分野を中心に他の診療所と連携しながら患者様の診療を行います。 この診療所と診療所の連携が診診連携です。
- 症例集
診断
肺高血圧症・慢性心不全
退院までの経過
高血圧症による慢性心不全で治療されていた。
2017年2月
インフルエンザ感染後心不全の急性増悪で入院
HOT導入
2017年8月
心不全の急性増悪にて再入院。シルデナフィル、イロプロスト導入
2017年10月
心不全の急性増悪にて再入院。シルデナフィル導入
2017年12月
心不全の急性増悪にて再入院。ドブタミン持続点滴
2018年1月
ドブタミン持続点滴を減量すると尿量低下し心不全の悪化をきたすカテコラミン依存性の為、ドブタミン2.5μg/㎏/min持続のまま退院となる。
退院後
末梢よりドブタミンの持続点滴継続のため定期巡回随時対応サービス利用となり毎日訪問看護が入り点滴の管理をする。中心静脈点滴ルートによる強心剤の点滴を提案するも本人拒否し、入院と同じように末梢からの点滴のため、点滴の閉塞、点滴漏れ予防のため3日に1回、ルート交換するが、日中、夜間に閉塞がみられ、訪看へ連絡があり直ちにルートをとり直すことが月2~3回ありその都度対応する。それでも退院後、BNP940から439まで改善し、食事量も増えベッド上生活が主体であるが安楽な在宅療養をおくった。毎日訪問看護にて点滴の交換、心不全状態のチェック、足湯などの保清、妻へのレスパイトなどの看護を行う。
退院後、2か月後より心不全の悪化がみられ、ドブタミン増量。
退院後、3か月後に心不全の増悪がみられ、ドブタミン増量するも症状の改善なくイロプロスト吸入増量とカルペリチドの点滴を追加し、心不全の増悪は改善する。心不全の増悪の原因が点滴漏れと考えられ本人の承認もあって中心静脈ルートからの持続点滴をする。
7月20日退院から6ヵ月をむかえ、うなぎを食べてお祝いする。
翌日朝より、感染徴候とともに心不全の悪化症状がみられ、利尿剤増量し、抗生剤開始する。翌々日午前、ポータブルトイレでの排泄中に突然意識消失し、ナースコールあり。心肺停止状態であったが、妻は救急依頼を断りそのまま看取りとなる。
診断
てんかんに伴う廃用症候群・脳幹部脳梗塞・非弁膜症性心房細動
病歴
40歳台でてんかん発症し、治療を継続しているが高齢となり次第に廃用症候群となりADLが低下し、外出困難で室内ならばつたい歩きで生活していた。
2017年7月、脳幹部脳梗塞に罹患し入院となりリハビリ病院転院してリハビリをするも寝たきり状態で、自分での坐位保持困難で自ら体位変換困難で食事は全介助の状態で安定した。要介護5の状態。
娘が介護職であり、寝たきりの祖母を在宅で看取った経験があり、本人の希望もあり在宅療養となる。
生活状況
独身の息子との2人暮らしであったが、息子は仕事のため夜遅くまで帰宅することができないことばしばしばあり、介護に関与することはなかった。
嫁に出た娘がキーパーソンで娘の勤務先がケアマネージャーとなり介護計画を作成している。1日2回、朝昼介護職が入り、夕方は娘が介護するが21時以降は一人のこともある状況であった。
1日の大半が一人暮らしであり、押しボタン式の緊急連絡装置の設置を申請したが、同居者がいる場合は認可されないため、息子が別居し安全な一人暮らしとなる。
経過
退院直後は何とか食事もとれていたが、充分でなく週3回の点滴にて水分補給をしたが次第に食事がとれなくなり、経口栄養剤も200ml飲むのがやっととなった。
2月中旬より中心静脈栄養とするが、内服剤の服用も困難になってきている上に筋力低下に伴う嚥下困難、呼吸筋不全が進行したため胃瘻造設を勧めていた。
6月、意識障害のため緊急入院となる。誤嚥性肺炎とてんかん発作、呼吸筋不全によるCO₂蓄積が意識障害と考えられ、胃瘻造設し、内服剤の確実な投与、栄養改善をはかることとなる。
退院後より定期巡回随時対応、訪問看護、介護サービスとなる。
1日のタイムスケジュール
訪問看護
胃瘻からの注入と管理・全身状態の観察と評価・肺理学療法
訪問介護
身体保清、体位変換、療養支援
週2回理学療法士によりリハビリ
8月中旬より全身倦怠、呼吸困難が強くなり、抑うつ状態となり“胃瘻の中止など”の訴えが多くなり、介護、看護とも随時対応を1日数回行うことがあるが内服剤の調整で落ち着く。
9月5日より痰の喀出困難が悪化し、随時対応で処置するが9月7日早朝より意識レベルの低下があり緊急入院となる。
肺炎併発、呼吸筋不全による換気障害が悪化し2週間後逝去される。
診断
心サルコイドーシスによる末期心不全
経過
10年前に胃癌で胃全摘出手術を受けている。5年前に心サルコイドーシスによる慢性心不全、心室性不整脈の為、外来治療を受けていたが、4月より食事が全くとれなくなって全身倦怠が強く、一人暮らしが困難な状態のため入院となる。
BNP1694と末期心不全の急性増悪の為治療を受け、症状は落ち着いたが、左心駆出率16%でBNP813と心機能低下が著しく、心臓リハビリを行っても活動量は2メッツ程度であり、一人暮らしは困難な状態であるが、可能な限り自宅で療養をしたいとの本人の希望もあり、看護小規模多機能居宅介護施設を選択される。
生活状況
独居で遠方の娘が時々帰省する。親交の深い友人2名、近隣の方の協力あり。
経済・制度的状況
医療保険:国民健康保険
食費負担:難病医療費助成制度費(自己負担限度額:5000円)
介護保険:要介護3
収入:老齢年金受給(日額:70000円)
住居:借家(一軒家:35000円)
身体障害者(心臓機能障害)3級申請中
看護小規模多機能居宅サービス利用状況
6月初旬退院直後から2週間
病院より退院された直後より、泊まりのサービスを開始し、ADLが改善し在宅療養可能な状態となるようにリハビリを行う。
理学療法士による心臓リハビリを開始。運動能力の改善に応じて終日ベッドで過ごす状態で食事はベッドサイドであったが、デイルールで食事を摂れるようになり、ポータブルトイレから室内トイレを利用するようになる。さらに、歩行訓練、入浴介助へとADL拡大をはかり2週間後より、自宅復帰となる。
退院2週間後からのサービス
週3回は通所サービスを利用。
週4日は自宅で過ごし、1日3回の訪問介護で(食事・排泄・掃除等の室内の管理、買物など)生活サポートする。週1回の訪問看護で心身状態をチェックしながら生活指導をする。週1回訪問リハビリにて自宅でのADL拡大をはかる。
経過
8月22日、自宅で転倒し胸椎圧迫骨折したため、自宅療養は困難となり泊まりのサービスを利用してリハビリ・心機能の安定をはかる。
9月9日に肺感染を併発したため、夜間呼吸困難出現し心不全の急性増悪がみられるようになる。内服剤の増量、利尿剤の静脈内投与でも心不全状態は改善しないため、強心剤(ドーパミン)の持続点滴を開始して、心不全症状は安定する。が、食事がとれない状況が続き、9月23日より中心静脈栄養を開始して、リハビリ栄養を行い病状は小康状態となる。
10月12日、炎症反応の悪化とともに心不全はさらなる急性増悪を呈し、強心剤、利尿剤の増量をはかるも著効せず、呼吸困難の訴えが多くなる。
10月14日、本人の希望、家族とのACPの結果、病院への入院はせず塩酸モルヒネによる鎮静をはかりながら心不全の治療を継続することとなる。
10月24日、看護小規模多機能居宅施設での看取りとなる。
非癌患者の緩和ケアの必要性の高まりの中で、心不全パンデミックといわれる心不全患者の急激な増加がみられはじめている昨今、末期心不全患者、特に高齢者末期心不全患者をどこで、どう見ていくかが課題となっております。
末期心不全者の緩和ケアは、癌患者の緩和ケアと違い、末期であっても病態が軽快・増悪を繰り返し、症状緩和には標準的な心不全の治療をうまく調整しながら、継続していくことが重要で、末期であっても必要に応じて積極的な治療をすることが病態の軽快をもたらしたり、症状緩和に有効なことは稀ではありません。
心不全治療ガイドラインによると心不全患者の呼吸困難の治療として、エビデンスがあって推奨されているのはループ利尿剤、ニトロ製剤の使用と、末期心不全時の少量のオピオイド投与です。エビデンスが充分ではないため、推奨されてはいませんが、カテコラミン等の強心剤の投与、呼吸困難、運動療法等の心不全リハビリ、酸素療法も有効性が示唆されています。2018 年から 2019 年の 2 年間に当院ならびに当院関連の訪問看護ステーション、看護小規模多機能居宅介護事業所「プルメリア」、医療サービス付高齢者住宅「プルメリア」にて経験した在宅にて「カテコラミン持続点滴」を施行した 6 例について、その有効性と課題を検討しました。
2018 年から 2019 年の 2 年間に当院ならびに当院関連の訪問看護ステーション、看護小規模多機能居宅介護事業所「プルメリア」、医療サービス付高齢者住宅「プルメリア」にて経験した在宅にて「カテコラミン持続点滴」を施行した 6 例について、その有効性と課題を検討しました。
当院で2021年6月より2022年5月の1年間に経験した急性心不全症例、慢性心不全の急性増悪(以後急性増悪)症例についての動向を検証しました
急性心不全状態で初診した方が7名、重症度分類ステージBで加療した方が急性心不全を発症して受診した方が18名、慢性心不全ステージCの状態で治療していた方が急性増悪された方が18名の計43名を診療しております。
急性心不全発症又は急性増悪時の年齢は男性80.8歳、女性86.8歳と平均寿命より1歳程度低い年齢での発症でした。2020年厚生労働省からの発表によると男性の28.4%、女性の52.5%が90歳時でも生存しておられ、80歳以上では癌による死亡者数よりも心血管病変による死亡者数が多くなり、死亡年齢最頻値は男性88歳、女性92歳であることから、超高齢者の慢性心不全を含めた心血管病の治療をいかにするかが開業医としての重要な課題と考えられます。
心不全発症後、総合医療センターで入院治療された方が18名、総合医療センターの外来での治療となった方が2名、市中病院へ紹介し入院治療された方が8名、当院での外来治療の継続で症状改善をはかった方が8名、当院関連の介護施設“サービス付高齢者向け住宅プルメリア”内で治療した方が6名、在宅のままで治療した方が1名でした。
総合医療センターへ紹介した患者さんはHFpEFの患者さんが50%で、クリニカルシナリオ1の重症な患者さんが多く入院中に、冠動脈形成術、カテーテルアブレーション等の非薬物治療を受けられている方がおられました。総合医療センター退院後は、約半数の患者さんが逆紹介され当院での慢性心不全の治療を継続しております。
市中病院へ紹介し入院の上で治療をしていただいた患者さんはHFpEF,HFmrEF病態の方がほとんどで、心不全として重症度はそう高くないか、超高齢で認知症を合併している方が多く、介護の都合等で、家族の方が希望された病院への紹介で治療となっております。
75%の患者さんが逆紹介され、退院後は当院の外来で治療を継続しております。
当院関連の“サービス付高齢者向け住宅プルメリア”に入居されており、心不全発症、急性増悪された患者さんは超高齢者が多く、施設入居前に病院での入院治療経験があり、その際に認知症の悪化、ADLの極端な低下がみられた経験があります、さらに御家族の方がcovid19感染の蔓延のため、入院すると面会ができないため、施設内での看取りを含めた治療を希望されておりました。施設内で従来の治療に加えた薬物療法や、時にはドブタミン持続点滴等の治療、さらには末期心不全の緩和ケアを行っております。
心不全発症、急性増悪しているものの酸素化が保たれ、ADLも低下していないか、本人が入院を希望されない場合は、外来治療で経過をみておりました。すべての方にエンレスト導入を含めた薬物療法の追加にて病状は落ち着いております。2名の方は自宅での介護力がないために、家族の方の希望で総合医療センターへ紹介し入院となっております。
御一人、他院から末期腎不全のため寝たきりとなったため、在宅療養目的で紹介を受けた患者さんが、拡張型心筋症の慢性心不全の急性増悪状態でした。すでに末期心不全、心臓悪液質状態で、本人家族とも在宅での看取りを希望されたため在宅にて心不全緩和ケアを行っております。
2022年5月末の時点で分かっている範囲内では43名中4名の方が亡くなられておりました。
心不全の原因疾患としては病院からの報告に比べれば、高血圧性心疾患と、心房細動を含めた不整脈患者が多くみられました。心不全となった基礎疾患としては、高血圧、CKD、糖尿病が多く心不全ステージBでの厳格なコントロール必要性が実感される状況でした。
また併存症としての心房細動への対応、ならびに認知機能低下した方への対応を今後考慮する必要があると考えられます。
急性増悪の誘因としては、患者側要因の方が医学的要因より多く関与している例が多く、患者側要因でも塩分・水分の過剰よりは、高齢者のフレイルとそれに伴う栄養不全、さらにはNYHAⅢ、Ⅳ度例の11~12%存在しているといわれている心臓悪液質がより重要となっていくのではないかと考えられます。
さらに老々介護であったり、認知症がこれらの病態をさらに修飾していく可能性があるため、在宅での心不全療養指導師の果たす役割が多くなると考えられます。
2022年1月1日より2022年12月31日までの1年間に当院で関わった末期患者は70歳代、80歳代を中心とした男性29名、女性25名の計54名でした。
原発病巣としては肺癌、大腸癌が最も多く全身のあらゆる癌患者さんの末期状態に緩和医療を提供させていただきました。
紹介元医療機関としては山口県立総合医療センターが最も多く、末期状態となって癌に対する積極的な治療が終了した後、在宅での緩和医療を希望され紹介された患者さんが多数を占められておりましたが、癌治療は県立総合医療センターの主治医の元で継続されながら、在宅生活での諸症状に対する緩和医療は当院が行なうというような主治医2人制的に対応した患者さんも少なからずおられました。
防府市内のみならず、山口市・宇部市の医療機関からの紹介をいただいております。
当院で治療中に癌が発見され、当院での治療と平行して癌治療を受けられていましたが、末期状態となって原疾患、緩和治療とも当院で継続したり、原疾患の重症度や認知症など背景病態のため癌治療の適応とならず緩和医療となった患者さんが6名、元々は癌治療を受けていたが、高齢、フレイルのため通院が困難となった患者さんが、寝たきりとなったため往診での対応を求められた例が4名おられました。
在宅緩和医療としては癌性疼痛コントロールを中心に多彩な症状緩和医療の他に、ストーマ管理、在宅酸素療法、胸水・腹水の穿刺、経管栄養、中心静脈栄養等、本人家族の求めに応じて必要とされる医療行為を行なっております。
癌性疼痛のコントロールのため、オピオイド使用者は35名でそのうち18名でオピオイドの持続皮下注又は持続点滴等の注射剤での鎮痛治療を行なうとともに、終末期には本人・家族の同意のもとでミタゾラム等による鎮静治療も行なっております。
癌性疼痛治療
- オピオイド使用者 35名
- オピオイド注射使用者 18名
当院での在宅緩和医療の転帰としては、在宅看取りとなった方が30名、最期は病院へ転院された方が12名、2022年12月末現在で治療中の方が12名いらっしゃいました。
転帰
- 在宅看取り 30名
- 転院 12名
- 治療継続中 12名
在宅で看取りとなった方々の看取りの場所は、自宅で看取りをした方が13名、当院関連の介護施設“プルメリア”へ入居(病院からの紹介直後から入居された方、自宅療養していたが終末期になって入居された方、看護小規模多機能型居宅介護“プルメリア”に登録され、終末期は同所への「宿泊」とういう形態をとられた方を含む)され、看取りとなった方が15名、別の介護施設で看取りとなった方が2名でした。
在宅看取りの場所
- 自宅 13名
- 介護施設
プルメリア 15名
その他 2名
当院での在宅緩和医療開始から1~3ヵ月の緩和医療の後、看取りとなった方が最も多くおられました。重篤な病態でも最後は家でという希望があり在宅へ戻られ数日で看取りとなった方もおられました。生命予後3~6ヵ月と診断されてた方の中には、在宅で生活することにより生活のリズムが戻り食事・睡眠が改善し癌性疼痛等の症状が緩和され本人の持つ生命力が回復し、事前の予想以上に在宅で生活することができた方も少なからずいらっしゃいました。
在宅看取りまでの療養期間
- 1週間以内 3名
- 1ヵ月以内 5名
- 1~3ヵ月 12名
- 3~6ヵ月 4名
- 6~12ヵ月 6名
在宅療養後転院となった方の転院先はすべて紹介元の病院に受け入れていただきました。県立総合医療センターには、オンコロジーエマージェンシーによる病態の急変時に時間外でも直ちに対応していただけており、在宅療養をしている当院にとっては大変ありがたい状況となっております。
自宅で転倒し腰椎圧迫骨折された際に受け入れていただいた桑陽病院、当院で診断後治療していた患者さんが急変した際、入居していた施設では看取りができないとのことで急遽入院を受け入れていただいた三田尻病院のスタッフの方にも感謝申し上げます。
非癌患者の緩和ケアの必要性の高まりの中で、心不全パンデミックといわれる心不全患者の急激な増加がみられはじめている昨今、末期心不全患者、特に高齢者末期心不全患者をどこで、どう見ていくかが課題となっております。
末期心不全者の緩和ケアは、癌患者の緩和ケアと違い、末期であっても病態が軽快・増悪を繰り返し、症状緩和には標準的な心不全の治療をうまく調整しながら、継続していくことが重要で、末期であっても必要に応じて積極的な治療をすることが病態の軽快をもたらしたり、症状緩和に有効なことは稀ではありません。
心不全治療ガイドラインによると心不全患者の呼吸困難の治療として、エビデンスがあって推奨されているのはループ利尿剤、ニトロ製剤の使用と、末期心不全時の少量のオピオイド投与です。エビデンスが充分ではないため、推奨されてはいませんが、カテコラミン等の強心剤の投与、呼吸困難、運動療法等の心不全リハビリ、酸素療法も有効性が示唆されています。2018 年から 2019 年の 2 年間に当院ならびに当院関連の訪問看護ステーション、看護小規模多機能居宅介護事業所「プルメリア」、医療サービス付高齢者住宅「プルメリア」にて経験した在宅にて「カテコラミン持続点滴」を施行した 6 例について、その有効性と課題を検討しました。
2018 年から 2019 年の 2 年間に当院ならびに当院関連の訪問看護ステーション、看護小規模多機能居宅介護事業所「プルメリア」、医療サービス付高齢者住宅「プルメリア」にて経験した在宅にて「カテコラミン持続点滴」を施行した 6 例について、その有効性と課題を検討しました。
2023年1月1日より2023年12月31日までの1年間に当院で加療した末期癌患者は男性26名、女性23名の計49名でした。
発生臓器別では肺癌、大腸癌患者さんが多くおられましたが、全身あらゆる癌患者さんの末期病態に関わらせていただきました。
紹介元医療機関としては県立医療センターからが最も多く山口大学医学部附属病院、山口宇部医療センターからも紹介を受けております。
新型コロナウイルス感染の蔓延によって家族の方の面会が制限された結果、ご本人もご家族も、みんなともに過ごし、みんなに囲まれて最期を迎えたいという方が、在宅療養を選択された傾向にありました。市中病院からの紹介も、多くは基幹病院から療養目的に転院されたものの、やはり自宅療養を選択された方が多くいらっしゃいました。
当院通院中又は当院受診された際に癌が発見され総合医療センターで癌治療を受けられながら当院にも併診され末期を迎えられた方が5名いらっしゃいました。
在宅療養中に新型コロナウイルス感染に罹患され、中等症の呼吸不全状態となられましたが入院すると家族の誰とも面会できなくなり、家族の看取りができなくなるため在宅酸素導入等を行ない自宅で看取った方もおられました。
本人、家族が求めに応じた医療行為(胸水、腹水穿刺、経管栄養、中心静脈栄養、在宅酸素導入、ストーマ管理等)を行っております。
癌性疼痛管理を要した患者さんは24名でそのうちの半数の方で注射剤による疼痛管理や終末期には鎮痛処置を行ってまいりました。
癌に対する積極的な治療が終了し、緩和医療の状態となってからの在宅療養期間は1~3ヵ月の方が最も多くいらっしゃいましたが、在宅療養となってから病院で予測された予後以上の期間を在宅で過ごされた方も多々ありました。
当院での在宅緩和医療ならびに訪問看護ステーションプルメリア、サービス付高齢者向け住宅プルメリア等での在宅緩和ケアの後、在宅看取りとなった方が31名、最期は病院へと転院された方が13名おられました。2023年12月末の時点での治療継続中の方が5名いらっしゃいます。
当院では2023年の1年間に48名の看取りを行っておりますが、そのうちの31名が末期癌患者の方々でした。
その看取りの場所は自宅で看取りとなった方が20名、サービス付高齢者向け住宅プルメリアに入居されそこで看取りとなった方が11名おられました。
2023年はやはり新型コロナウイルス蔓延のため在宅で看取る方が多くいらっしゃいました。
当院での在宅看取りまでの療養期間としては療養開始後から1~3ヵ月間の自宅療養という方が最も多くいらっしゃいました。
ご本人が最期は家で過ごしたいという強い希望のため自宅に戻られ数日で看取りとなった方々もいらっしゃいました。
病院では予後3~6ヵ月と言われていた方の中には在宅療養で予想された以上に生活された方も少なからずいらっしゃいました。
毎年のことですが、県立総合医療センターの皆様には、病状の急変時や本人・家族の想いの急転時に時間外でも転院を受け入れていただいており、患者家族の方々から感謝されております。
それ以上に在宅療養を担当している当院にとっては大変ありがたく思っております。
さらに本来の癌以外の病態で入院が必要となった場合や、元の紹介先が遠方のため家族が地元の病院で看取りを希望された際に受け入れていただいた三田尻病院、三祐病院の皆様にも感謝申し上げます。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
詳しくは以下の資料をご覧ください。
- 医療連携実績
当院からの紹介件数
| 総合医療センター | 市内病院 | 市外病院 | 診療所・医院 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月分 | 28 | 29 | 3 | 4 |
| 令和7年2月分 | 29 | 32 | 3 | 2 |
| 令和7年3月分 | 21 | 16 | 3 | 5 |
| 令和7年4月分 | 28 | 19 | 7 | 6 |
| 令和7年5月分 | 16 | 15 | 4 | 10 |
| 令和7年6月分 | 12 | 25 | 5 | 4 |
| 令和7年7月分 | 28 | 21 | 2 | 6 |
| 令和7年8月分 | 19 | 19 | 0 | 11 |
| 令和7年9月分 | 21 | 22 | 1 | 7 |
| 令和7年10月分 | 20 | 26 | 3 | 5 |
| 令和7年11月分 | 21 | 9 | 3 | 4 |
| 令和6年の年間トータル | 227 | 279 | 41 | 62 |
| 令和5年の年間トータル | 194 | 240 | 31 | 69 |
| 令和4年の年間トータル | 189 | 266 | 44 | 78 |
| 令和3年の年間トータル | 283 | 288 | 26 | 84 |
| 令和2年の年間トータル | 227 | 249 | 29 | 86 |
| 平成31年・令和元年の 年間トータル | 208 | 243 | 30 | 81 |
| 平成30年の年間トータル | 137 | 284 | 26 | 110 |
| 平成29年の年間トータル | 171 | 211 | 44 | 89 |
| 平成28年の年間トータル | 202 | 274 | 35 | 129 |
当院への紹介件数
| 総合医療センター | 市内病院 | 市外病院 | 診療所・医院 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月分 | 9 | 4 | 2 | 5 |
| 令和7年2月分 | 8 | 10 | 5 | 4 |
| 令和7年3月分 | 23 | 8 | 4 | 2 |
| 令和7年4月分 | 18 | 9 | 5 | 3 |
| 令和7年5月分 | 20 | 7 | 3 | 5 |
| 令和7年6月分 | 12 | 4 | 2 | 2 |
| 令和7年7月分 | 17 | 6 | 8 | 3 |
| 令和7年8月分 | 13 | 3 | 5 | 2 |
| 令和7年9月分 | 8 | 4 | 2 | 3 |
| 令和7年10月分 | 12 | 7 | 3 | 2 |
| 令和7年11月分 | 10 | 2 | 2 | 1 |
| 令和6年の年間トータル | 150 | 96 | 41 | 57 |
| 令和5年の年間トータル | 146 | 98 | 32 | 56 |
| 令和4年の年間トータル | 157 | 95 | 44 | 55 |
| 令和3年の年間トータル | 142 | 74 | 39 | 69 |
| 令和2年の年間トータル | 102 | 51 | 32 | 40 |
| 平成31年・令和元年の 年間トータル | 115 | 64 | 31 | 44 |
| 平成30年の年間トータル | 130 | 84 | 27 | 43 |
| 平成29年の年間トータル | 121 | 76 | 32 | 41 |
| 平成28年の年間トータル | 149 | 48 | 35 | 40 |